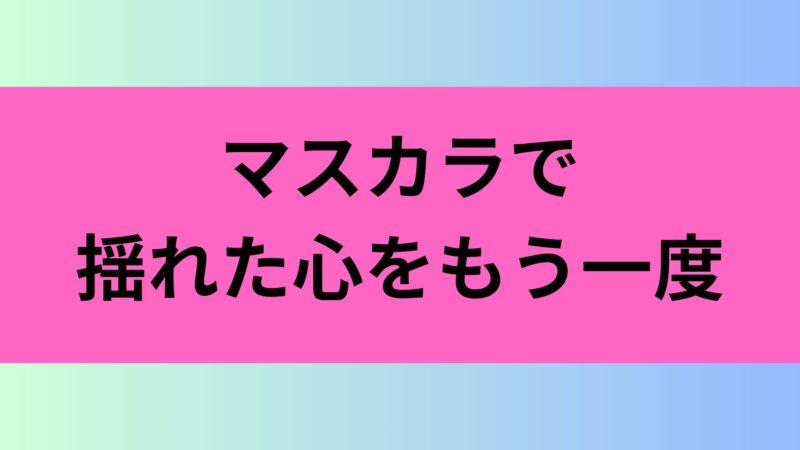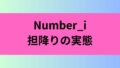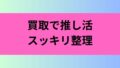マスカラをきっかけに、SixTONESへの気持ちが少し揺らいだことはありませんか?
あの頃の勢いが懐かしくて、どこか冷めた自分に戸惑ったり、人気落ちたのではと感じたりする瞬間は、多くのファンが経験しているものです。
マスカラがひどい、マスカラに批判が多いという声を目にして、複雑な気持ちになった人もいるでしょう。
ゴールデン番組に出ているSixTONESが面白くないと感じたり、最近の方向性に良さがわからないと思う人もいるかもしれません。
一方で、担降りをリアルタイムで考えながらも、心のどこかではまだSixTONESを信じたいという想いを抱えている人も少なくありません。
この記事では、マスカラ期のファン離れの背景や人気ない理由を客観的に見つめ直しながら、SixTONESの今とこれからを一緒に考えていきます。
一度冷めた気持ちを、もう一度あの熱に変えるために――SixTONESを愛するファンだからこそ見える“本当の変化”を紐解いていきましょう。
【sixtones】マスカラで担降りが増えた背景を探る
マスカラリリース後に気持ちが離れたのは?
「マスカラ」がリリースされた時、多くのファンが「SixTONESの新しい一面を見た」と感じた一方で、少しずつ気持ちが離れていった人もいました。
その理由のひとつは、グループの方向性の変化にあります。Jr.時代のSixTONESは、尖った魅力やギラギラとした勢いが印象的でした。ステージでは爆発的なエネルギーを放ち、見ているだけで心を掴まれるような“熱”があったのです。
ところが、「マスカラ」ではその熱量が落ち着き、繊細で芸術的な表現に比重が移りました。もちろん楽曲としての完成度は高く、美しいメロディと歌詞の世界観は唯一無二です。ただ、その静けさや余白が、これまでSixTONESの“勢い”に魅了されてきたファンには少し寂しく映ったのかもしれません。
SNSでも、「大人っぽくなったけど、以前のエネルギーが恋しい」「クールだけど心に届きにくい」といった声が多く見られました。
ファンの心が離れたのは、単なる好みの問題ではなく、SixTONESという存在の“変化の節目”に、ついていけなかったという複雑な感情があったからです。要するに、好きだからこそ戸惑い、好きだからこそ距離を取らざるを得なかった——そんな心情を抱いた人が多かった時期だったのです。
マスカラがひどいと言われる理由
「マスカラ」が“ひどい”といわれることがありますが、実際には楽曲の質というよりも、“期待とのギャップ”が原因だったと考えられます。SixTONESに対して多くのファンが抱いていたのは、「力強さ」「男らしさ」「爆発的なパフォーマンス」というイメージでした。ところが、「マスカラ」ではその真逆をいくような、静かな情感と美しさを前面に出した表現に変わったのです。
このギャップが、特に長年のファンにとって戸惑いを生みました。歌詞もメロディも非常に繊細で、感情を抑えた構成だからこそ、初めて聴いた時には“難しい”と感じる人が多かったのも無理はありません。
また、当時のテレビパフォーマンスでは、照明や演出も含めて“アート寄り”の印象が強く、感情の起伏を視覚的に感じ取りづらい部分もありました。SNS上では「暗くて重たい」「SixTONESらしさがない」といった反応が拡散され、結果的に“ひどい”という表現で一括りにされてしまったのです。
とはいえ、時間が経つにつれて「マスカラ」の良さを再評価する声も増えています。歌詞の繊細さや表現の深さが理解されるにつれ、あの曲がSixTONESにとって大きな挑戦だったことが明確になりました。要するに、“ひどい”という評価の裏には、それだけSixTONESへの“期待の高さ”があったということです。
マスカラに批判が広がった要因
「マスカラ」への批判が拡大したのは、単に曲の評価にとどまらず、ファンとの関係性が揺らいだタイミングと重なったからです。
まず、メンバーの発言やコメントの受け取られ方が大きく影響しました。ブログやインタビューの一部の言葉が「感謝が足りない」「ファンを軽く見ているように聞こえる」と感じた人が増え、モヤモヤが広がりました。
特に、CD販売を支えてきたファンにとっては、「自分たちの努力が伝わっていない」と思える瞬間があり、その失望感が大きな痛手になったのです。
さらに、ファンコミュニティ内での温度差も顕著でした。長く支えてきた古参ファンは「SixTONESが変わった」と感じ、一方で新規ファンは「今の方がかっこいい」と評価する。このすれ違いがSNS上で激しくぶつかり、ファン同士の対立を招きました。その結果、「ファンの雰囲気が悪い」「民度が下がった」といった印象が拡散し、SixTONES全体のイメージにも影を落としました。
また、アーティスティックな方向性を重視した結果、売上や話題性が以前より落ち着いて見えたことも批判を後押ししました。「SixTONES、人気落ちた?」という言葉が飛び交い、ファンの焦りがSNSで増幅されていったのです。
こうして“誤解と熱量のすれ違い”が連鎖し、「マスカラ」はSixTONESにとってファンとの信頼を試される一曲になりました。
ファン離れを加速させた出来事
ファン離れが進んだ背景には、いくつかの出来事が重なっています。ひとつは、「マスカラ」期の表現スタイルの変化。Jr.時代から応援してきたファンは、“勢いと野心”のSixTONESを好んでいたため、アート性の高い静かな曲調が続いたことで「昔のSixTONESが恋しい」という声が増えました。
もうひとつは、コミュニケーションのズレです。メンバーの発信やコメントのトーンが、支えてきたファンの気持ちと噛み合わない時期がありました。特に「感謝の言葉が伝わってこない」「少し距離を感じる」といった印象を持つ人が多く、熱量の低下につながりました。
そして、ファン同士の摩擦も避けられませんでした。SNS上で「新規 vs 古参」「本気で応援する派 vs ライト層」という対立が生まれ、応援の場が居心地の悪い空気に変わっていったのです。純粋にSixTONESを楽しみたい人ほど、距離を置く選択をした時期でした。
これらの要素が同時に重なったことで、「推すのが少し疲れた」という感情が広がり、ファン離れを加速させる結果となりました。
冷めたファンが増えたきっかけ
“冷めた”と感じたファンが増えたのは、決して突然のことではありません。日々の小さな違和感が積み重なった結果です。
Jr.期のSixTONESには、ライブでの爆発力やYouTubeでの自由な空気がありました。ところが、デビュー後は洗練された表現が増える一方で、“素のSixTONES”を感じる瞬間が減ったように感じる人が多くなりました。「最近、距離を感じる」「あの頃のワクワク感がなくなった」――そんな声が増えていったのです。
さらに、SNSや動画の更新ペース、リアクションのトーンにも影響がありました。企画内容や露出の偏りが続くと、「なんとなく見る頻度が減った」「熱が続かない」という状態になりやすくなります。ファン活動が“日常の楽しみ”から“惰性”に変わる瞬間、それが冷める分岐点でした。
また、発言や行動のニュアンスに違和感を抱いたり、他グループの魅力に触れる中で「もう少し安心して推したい」と思う人が増えたことも一因です。推し方が多様化した現代では、“好きの形”が変わるのは自然なこと。だからこそSixTONESに求められるのは、ファンが安心して気持ちを預けられる環境をつくることだと感じます。
人気落ちたと感じる瞬間とは
「人気が落ちた」と感じるのは、数字よりも“体感の変化”によるものが大きいです。CDの売上やSNSのトレンド滞在時間、YouTubeの再生数など、可視的な指標が前作より伸びないと、「勢いがなくなった」と思われやすくなります。しかし、実際にはファンの熱量が消えたわけではなく、活動の見え方が変わっただけというケースも多いのです。
特に「マスカラ」期のように芸術性を重視した時期は、バラエティなどの露出が減ったことで一般層の接点が減り、“静かな時期”に見えた部分がありました。その結果、「前より話題にならない」「勢いが落ちた」と感じる人が増えたのです。
ただし、コアなファンが離れていない限り、SixTONESの基盤は強固です。ライブ動員や配信成績、ソロ活動などを見ても、根強い支持は変わっていません。
つまり、「人気落ちた」と感じる瞬間は、SixTONESの音楽性が成熟している証でもあります。派手さや話題性だけではなく、作品の中身で勝負するフェーズに入ったということです。これからは、再び“熱狂”と“深み”を両立させるステージが待っているはずです。
【sixtones】マスカラでの担降りから見える今後の課題
ゴールデンでのSixTONESが面白くない?
ゴールデン帯に出ているSixTONESを見て、「普段の面白さが映らない」と感じる瞬間があります。理由のひとつは、番組の尺と編集テンポにあります。短いコーナーで結果が求められる場面では、SixTONES特有の“じわじわ伝わる掛け合い”や、関係性から生まれるツッコミ合いが十分に伝わる前に切り替わってしまいます。Jr.期の自由度が高い動画やコンサートMCのように、空気感を温めてから笑いに落とすスタイルは、ゴールデンの速度とは相性が悪いことがあります。
もう一つは、フォーマット適応の難しさです。クイズ系、リアクション系、体張りロケ系など、それぞれの“勝ち筋”が異なります。複数人で出演する際に、出だしの一言や最初のボケ・ツッコミを誰が担うのかが曖昧だと、見せ場が散らばり、編集で削られやすくなります。逆に、代表スピーカーが素早く場をつかみ、他メンバーが“回し・ツッコミ・オチ”へ役割を寄せると、短時間でもキャラが立ちやすくなります。
音楽番組やライブドキュメントのように、歌と表情で魅せる枠では存在感が際立ちます。したがって、ゴールデンで“面白くない”と受け取られないためには、番組の設計に応じて「最初の一言」「リアクションの粒立ち」「役割分担」を事前にそろえることが鍵になります。ファンとしては、その準備が伝わった回ほど爪痕がくっきり残ると感じます。
| 視聴者が抱きやすい違和感 | 背景にある要因 | 放送で映えるための工夫 |
|---|---|---|
| 面白さが届く前に切り替わる | 尺・編集テンポが速い | 代表スピーカーの明確化、冒頭フックの用意 |
| 誰が回すのか分かりにくい | 役割分担が曖昧 | 回し・ボケ・ツッコミの事前合意 |
| 反応が薄く見える | 企画との相性・慣れ不足 | 企画別“勝ち筋”の共有と練習クリップ |
人気ない理由を客観的に考察
「人気がない」と感じられるときは、実態よりも“見え方”の要素が強く働いています。たとえば、発売初週の数値が前作比で横ばいだったり、トレンド入りの滞在時間が短かったりすると、勢いが落ちた印象が先に広がります。難易度の高い楽曲が続いた時期には、テレビ初見のリスナーにキャッチーなフックが届きにくく、サビや振り付けの真似が広がらないことで、話題の循環も生まれにくくなります。
露出の質と量も体感に影響します。ゴールデン帯での強いハイライトが続かない週が重なると、ライト層の入口が細くなり、SNSの自発的な拡散が鈍ります。加えて、ファンコミュニティ内の温度差が可視化されるタイミングでは、摩擦の話題が音楽の話題を上書きしやすく、外側には“盛り上がりが落ちた”ように映ります。
一方で、ライブ動員や個人活動の評価、ストリーミングの底堅さのような“地力”の指標は、短期の体感に比べてぶれ幅が小さいものです。したがって、体感を押し上げるには、初見に刺さる一曲や短尺で回る動画、そしてファンの努力をまっすぐ称える言葉を短いサイクルで回すことが有効だと感じます。表に現れる“話題”を連続させることで、実態と体感のギャップは徐々に縮まっていきます。
良さがわからない層の心理とは?
良さが伝わらない多くのケースは、入口体験でつまずいています。最初に触れた曲が難曲だったり、演出が内省的だったりすると、歌詞やコーラスワークの妙に到達する前に「難しい」で止まってしまいます。メンバーの個性が豊かなぶん、誰を軸に見ればいいのか分からず、情報量の多さに圧倒されて離脱することもあります。
比較対象の存在も心理に影響します。すでに“自分の基準”を持つリスナーは、そのグループのテンポ感や声質、ダンスの系統で新規グループを判断します。そこにズレがあると、優劣ではなく嗜好の違いとして距離が生まれます。また、先にバラエティの印象が固まり、音楽面の強みを体験する前に「自分向けではない」と決めてしまうパターンも少なくありません。
この壁を越えるには、入口の設計が決め手になります。ライブで“感情の頂点”が見える映像や、キャラと歌声が同時に分かる短尺クリップ、歌番組のベストパフォーマンスへのガイドを用意すると、最初の数分で魅力の核心に触れやすくなります。メンバーごとの強みをひと言で示す“理解のハンドル”があると、誰から入るかが明確になり、沼落ちへのスピードが一気に上がります。
ファンが再び熱を取り戻すには?
熱量を取り戻すカギは、「共感」「参加」「信頼」を循環させることにあります。まずは、発信の一つひとつに温度を込めることです。活動の舞台裏や制作過程、迷いも含めて言葉で届けられると、ファンは“自分たちの声が届いている”と実感できます。ライブや配信での双方向の仕掛け、SNSでのミニ企画や手書きメッセージのような“人肌感”のある発信は、熱を戻す近道になります。
次に、楽曲ラインアップのバランスです。挑戦的でアート志向の曲に加えて、即時性のあるアンセムやコール&レスポンスが映える一曲を定期的に差し込むと、ライブとテレビの両面で“今のSixTONES”が鮮やかに伝わります。ダンス・コーラス・ラップの見せ場がはっきり分かる構成は、ライト層の参加も後押しします。
そして、感謝と歩み寄りのメッセージは何よりも強い力を持ちます。数字や達成の報告だけでなく、「あなたたちの応援が背中を押してくれた」という言葉が、長く支えてきたファンの心をもう一度温めます。小さな“ありがとう”を積み重ねることが、熱量の再点火につながります。
グループが進むべき方向性を考える
これからのSixTONESに必要なのは、アーティスト性とエンタメ性の“心地よい交差点”を定義することだと感じます。音楽的な挑戦は続けつつ、ライブ・テレビ・SNSの各接点で“一発で伝わるフック”を用意する。たとえば、コーラスの厚みを前面に出す楽曲と、視覚的に記憶される振り付けを組み合わせると、深みとわかりやすさが両立します。
物語の再構築も欠かせません。デビュー初期の“挑戦するSixTONES”から、今は“成熟して選び抜くSixTONES”へ。何を大事にし、何を手放し、どこへ向かうのか――その意思をドキュメンタリーやメンバー発案のライブ演出で可視化できると、ファンは歩幅を合わせやすくなります。個々の強み(演技、作詞作曲、ダンス、MC力)をグループの一本の線で結ぶ編集も、有効です。
最後に、現場の設計力です。バラエティでは役割分担と“最初の一言”、音楽番組ではカメラ割りとコーラスの聴かせ方、SNSでは短尺でのキャラ提示。接点ごとに最適解を持ち、同時多発的に“らしさ”を届けられれば、体感の波は自然と上向きます。要するに、SixTONESの核はすでに強いので、それを“届く形”に整える段取りが次の飛躍を生みます。
【sixtones】マスカラで担降りが増えた背景のまとめ
記事をまとめます。